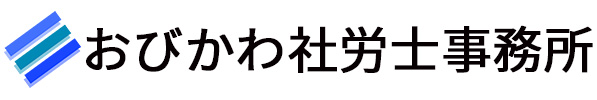フジテレビで明らかになった人権侵害の内容
2025年3月31日、フジテレビの第三者委員会は調査報告書(394ページ)を公表し、当時フジテレビの女性アナウンサーだった被害者Aさんが元SMAPメンバー中居正広氏から業務の延長線上で性暴力を受けたことを認定しました。この事件は2023年6月2日、中居氏の自宅マンションで発生し、委員会は女性Aさんの証言などに基づき「重大な人権侵害」であると結論づけています。
報告書はまた、フジテレビ経営陣の対応の問題点を厳しく指摘しています。被害女性が社内に被害を申告した際、当時の港浩一社長や大多亮専務(現関西テレビ社長)ら幹部3名は、この案件を「私的な男女間のトラブル」と誤って判断し、自社の人権問題との認識を欠いた対応をとりました。彼らはフジテレビの人権方針に基づく措置や外部専門家への相談を行わず、結果的に被害者に寄り添った適切な救済措置を取らなかったとされています。このような判断は「極めて思慮の浅い判断」であり、フジテレビにおける本件対応の誤りの大きな要因と報告書で厳しく非難されました。
スポンサー企業のCM出稿停止対応
この性的被害問題が報道で明るみに出た今年1月以降、多数のスポンサー企業がフジテレビへのCM出稿を一斉に停止する措置を取りました。ダイヤモンド社の調査によれば、2025年1月中旬にフジテレビでCMを流していた企業・団体435社のうち、回答が得られた中で「広告出稿を打ち切った」が161社に上り、その他「当面の出稿見合わせ(ACジャパンの公共広告に差し替え等)」と回答した企業も50以上に及びました。合計すると200社以上が事実上CMを取りやめた計算で、トヨタ自動車、明治安田生命、日本生命、サントリーHD、キリンHD、日清食品HD、象印マホービン、アフラック生命、NTT東日本、花王、日産自動車など日本を代表する企業が名を連ねています。わずか数社(法律事務所など公共性の高い内容を扱う一部)を除き、フジテレビのCM枠は公共広告(ACジャパン)だらけになる異常事態となりました。
各社がCM停止に踏み切った理由として共通するのは、企業として人権問題に適切に対応する姿勢を示すためです。たとえば、キリンホールディングスは公式見解で「当社は国連『ビジネスと人権に関する指導原則』に則り人権方針の遵守を全てのビジネスパートナーに求めている。今回の一連の報道でもフジテレビ社の対応を注視してきたが、記者会見での説明等を踏まえ、必要な調査が十分行われ事実が明らかにされ適切な対応がなされるまで、同社への広告出稿を停止する」と表明しました。トヨタ自動車も1月18日にCM差し止めを決定し、「お客様やステークホルダーの共感を得られる形でメディア出稿したい」との姿勢を示しています。さらに、日本生命は「再発防止策の内容の妥当性と適切な実行が重要であり、現時点で直ちにCMを再開しない」と述べ、味の素やローソンも「再開は未定」として慎重な立場をとりました。キッコーマンは提供番組「くいしん坊!万才」を1月26日放送分から休止するようフジに要請するなど、番組単位での対応も見られました。各社とも、自社の企業倫理やステークホルダーからの信頼を守るため、フジテレビ側の調査と対策が十分になるまで広告出稿を見合わせる判断を下したと言えます。
ビジネスと人権に関する国際基準の関連ポイント(ILO・UNGP)
国際労働機関(ILO)や国連の『ビジネスと人権に関する指導原則(UNGP)』は、企業に対して自社およびビジネスパートナーにおける人権尊重を求めています。特に重要なのは、問題発生時の救済(リメディ)、エンゲージメント(関与・対話)、是正措置に関する原則です。
UNGPでは「企業は自らの活動や取引関係を通じて人権への負の影響に関与しうる」とし、そのような状況への対処法を定めています。原則22では、既に生じてしまった人権被害に対しては適切な是正(救済)措置が講じられるべきだと明記されています。つまり、被害者に対する謝罪や補償、再発防止策の実施など、発生した被害への対応・救済が不可欠です。また原則18では、人権デューデリジェンスにおいてステークホルダー(利害関係者)との対話・エンゲージメントが強調されており、企業は被害を受けうる当事者の声を聞き、意見を取り入れる努力が求められます(例えば被害者や労働組合との協議など)。さらに原則19では、企業が取引先による人権侵害リスクを把握した場合の対応について述べられており、企業はビジネスパートナーに対して働きかけ(レバレッジ)を行い、問題解決や是正を促す義務があります。直接に自社が原因でない場合でも、取引関係上深く関与しているなら、単に無関係を装うのではなく積極的に関与し改善を求める姿勢が求められるわけです。ILOの多国籍企業行動原則など国際基準も同様に、企業が取引先に対して人権尊重を促し、深刻な場合には適切な措置を取ること(場合によっては取引見直しも含む)が必要だとしています。
スポンサーの即時取引停止は国際原則上適切だったか?
今回のスポンサー各社による即時のCM出稿停止(取引停止)対応について、国際原則に照らした評価は一概に割り切れるものではありません。UNGPやILOは、企業に人権侵害への関与の回避と救済への関与を求める一方で、安易な関係解消は慎重に判断すべきとしています。特にUNGP解説では、ビジネスパートナーとの関係終了は「拙速なリアクションではなく、人権への影響を十分評価した上で判断すべき」とされ、**「まずはエンゲージメント(対話)とレバレッジの行使によって是正を図り、それでも改善しない場合の最終手段として取引停止を検討する」**というアプローチが推奨されています。
この観点から見ると、スポンサー企業がただちに広告を引き上げた行為は一見「拙速な取引停止」にも映ります。第三者委員会の調査結果や再発防止策の発表を待たずに撤退することは、UNGPの求める「まず関与して問題解決を促す」という姿勢に反するとの指摘もあり得ます。被害者救済という点でも、スポンサーが離脱しただけでは直接的な補償や謝罪が実現するわけではありません。むしろ収入源を失った放送局側が被害者への補償や改善投資に支障を来すリスクも理論上は考えられます。ILOの示す労使間の対話重視の精神からも、取引先を即座に排除するのではなく、事実関係の調査や改善策の協議にスポンサーとして建設的に関与することが理想的とも言えるでしょう。
しかし一方で、今回のケースは重大な性的暴力事件であり、初動対応で経営陣が問題を矮小化した経緯もあって、スポンサー各社は自社の人権方針に照らし看過できないと判断しました。実際にキリンHDのように明確な基準を示した企業もあり、彼らはUNGPに基づく**「人権侵害に対する許容ゼロ」の姿勢を示したと言えます。スポンサー離脱という強い措置は、フジテレビに対して徹底調査と再発防止策の確立を促す圧力(レバレッジ)の行使でもありました。その結果、フジテレビは追加の記者会見や社長辞任、第三者委員会設置といった対応を次々に行い、最終的に事実認定と謝罪、再発防止策の策定に至っています。つまりスポンサーの行動は企業市民としての責任行動であり、必ずしも国際原則に反したものではなく、むしろ人権尊重を徹底させるための実力行使として評価できる側面もあります。特に今回は一時的な「出稿停止」であって完全な契約解除ではなく、各社とも「適切な対応がなされるまでの措置」としており、改善後の再開余地を残しています。これはUNGPが推奨する「改善を促しつつ状況を見極める」アプローチにも合致するでしょう。総じて、スポンサー各社の対応は迅速かつ厳しいものでしたが、重大性に鑑みれば企業の人権責任上必要なリスク管理措置**だったと分析できます。
今後企業が取るべき行動と提言
今回の事態は、日本企業にとって**「ビジネスと人権」への実践が問われたケース**となりました。今後、スポンサー企業を含む全ての企業には以下のような取り組みが求められます。
- 人権デューデリジェンスの徹底: 取引先で重大な人権リスクが発覚した場合に備え、平時から人権方針に基づく調査・モニタリング体制を構築し、問題兆候の早期把握と対処を図る。特にメディア業界など多様な利害関係者がいる分野では、スポンサーも含めた外部からの指摘を真摯に受け止める仕組みが重要です。
- ステークホルダーエンゲージメント: 被害者や従業員、視聴者など影響を受ける当事者との対話を重視し、声を政策や対応策に反映させること。企業は問題発生時に社内だけで判断を完結させず、必要に応じて外部有識者やNGOとも協議して最善策を探るべきです。
- 段階的な是正措置とレバレッジ行使: 取引先に問題が起きた際、直ちに契約打ち切りとするかどうかはケースバイケースですが、まずは改善を促す段階的措置を検討すべきです。例えば警告や是正要求、一定期間の広告見合わせと改善計画の提出要求など、関与しつつ圧力をかける手法が考えられます。それでも改善が見られない、あるいは誠意ある対応が得られない場合に初めて契約関係の再考(長期停止や撤退)を検討するのが望ましいでしょう。
- 被害者救済への支援: 自社が直接の当事者でなくとも、人権侵害の被害者への救済が適切に行われるよう支援・フォローする姿勢も求められます。今回の件でも、スポンサー企業がフジテレビの対応を注視し続けることで、被害女性への謝罪や必要なケアが確実に実施されるよう間接的に促す役割を果たし得ます。企業は自社の利益やイメージだけでなく、広く人権擁護の観点から行動することが期待されています。
最後に、企業は**「自社と繋がる全てのバリューチェーンで人権が尊重されるようにする」という国際基準の要請を肝に銘じる必要があります。今回のスポンサー離脱は異例とも言える規模でしたが、それだけ企業が人権問題に本気で取り組まねばならない時代**に入った表れです。今後は、より多くの企業がILOやUNGPの原則を実経営に落とし込み、問題発生時には毅然かつ建設的な対応を取ることで、ビジネス界全体の人権意識向上と信頼回復に努めていくことが求められるでしょう。